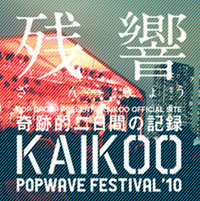皆さん初めまして、多くの人々のすなるブログというもの我もせんとて、ってな感じでブログってのをやってみることになりました。
今まで公にコミットする形で言葉で何かを伝えるってゆうのは頼まれた雑誌の原稿とか、自分や他のアーティストのプログラムに書いたりとか、そうゆうのを昔ちょっとやったぐらいで、極力避けて来たんだけど、お膳立てしてくれるスタッフの「何でも好きなことを好きなように気楽に書いてください、書けるときでいいですから。」というのに誘いだされてというか、還暦を目前にして、なんかいいたいことがいっぱいあるような気がして来てブログってのがなんなのかよくわかんないままに、もういいたい放題、誤解を恐れずに書いちゃおうっていう感じです。
第一回目はちょうど今やってる山海塾の日本公演新作「からみ」の東京初演の初日と、前作「とばり」の初日を見て来たので、そのへんからいこうかな。
舞踏との関わりは時代を遡って、1972年の土方巽『四季の為の二十七晩』、当時の新宿文化センターという映画館で27日間、毎晩映画の終わった後に舞台を作って、たしか5つの作品だったと思うけど、2階客席の両側にあった張り出し席の上手のほうにはまだご健在だった津軽三味線の名手、木田林松栄さんが、そして下手に<音響箱>と土方さんが名付けた御簾で囲ったスペースに、ステンレスの板とかいくつかの楽器というか音の出るものをセットして、主に土方さんのソロの場面で生演奏をしたのが最初です。舞踏の創始者というか、もうその頃から伝説になってたような土方さんとのことを、衝撃的だった出会いから書こうと思うとそれだけで一冊本が書けそうな気がしちゃうから、また別の機会にするけど、二十歳そこそこの自分が毎晩、ほとんどステンレスの板一枚だけから生み出される響きで稀代の舞踏家と対峙した経験はその後の自分の在り方にとんでもない影響をおよぼしたことだけは言っておきます。
音楽というか音の響きというものに対しての彼の耳というか感性の鋭さは半端じゃなくて、何度か、何かとても深いところで、大げさにいうとほとんど宇宙的なスケールで交響している感じっていうんだろうか、絶妙で鮮烈な至福の瞬間があったのを昨日のことのように覚えています。
'73年の西武劇場こけら落とし公演「静かな家」の後、'74年の9月から一人で、初めての海外へほとんど何の情報も持たずに、インドネシアのジャワからバリ島へ、結果として4ヶ月半にわたる、度重なる偶然と驚きに満ちた不思議な旅に出るんだけど、そのときは、生前の土方さんとの仕事がそれっきりになるなんて夢にも思わなかったわけです。
11年後に、バリ島との関わりの一区切りとなった、'85年プリアタン村歌舞団日本ツアー、国立劇場公演の最終日に、芦川さんと二人で観に来てくれて、帰り際に「佐藤君、これは君がやったのかい?」「いえ、コーディネイトしただけです、これが片付いたら伺いたいと思います。」ということで、年末に後始末の為にバリ島に入って、年を越して帰国、三日目に新聞の死亡広告を見て愕然としました。これからあらためて土方さんとの仕事に本格的に参入しようと心に決めて帰って来た矢先だったから、本当に残念でなりませんでした。2003年に「夏の嵐」で音楽を担当したんだけども、やっぱり、まだご健在なうちに、もう一度ご一緒したかったというのが本音です。晩年に、アスベスト館という彼のスタジオにお邪魔したとき、「佐藤、人ってのは残念ながら死なないんだよな。」と、ふともらした謎のような言葉を思い出します。
で、山海塾にもどるけど。実をいうとね、前作「とばり」を二年前に日本初演の初日で観たときも今回の新作「からみ」の初演も面白くなかったんだよね。そのまた二年前の作品「とき」がすごくよかったから友達をいっぱい連れていったんだけど、みんなでがっかりしてた訳です。
ところがね、今回再演の「とばり」を昨日(2月3日)観て来たんだけども、素晴らしかった訳。終わってから楽屋裏にリーダーの天児さんにお祝いをいいに行って話したんだけど、振り付けから照明から何から何まで変えてないっていう訳よ、僕には照明が前のときより少し暗めになったような気がしてたんだけど、それも変えてないっていう訳。前回も今回も吉田さんという友人と一緒に観たんだけども、彼も僕ももう全く違う作品を観てるような気がしてたんだけどね、同じ劇場でおんなじシチュエイションでこの違いは何なんだろうってことになる訳です。そしたら山海塾の音楽を長年やってるもう一人のミュージシャンの吉川君が新作の「からみ」も楽日(最後の日)はすごくよかったっていうんだよね。「とばり」はつい最近までアメリカツアーで踊り込んできたらしい。
やっぱりパフォーマンスそのものの出来不出来、つまりは踊りそのものの力によって、全く同じ作品が素晴らしくもなりまたつまらないものにもなってしまうという、まあ当たり前の話だけども、あらためてダンスと言うものの生ものさ加減を思い知らされた訳です。
いくら入念に振り付けされ演出されていても一つ一つの舞台の一回性が決定的なものである踊りというのは本当に厳しいもんだなあと。それを営々と世界を舞台に続けて来て今日の評価を獲得して来た山海塾と天児(あまがつ)さんにあらためて敬意を表したいし、音楽をやっている自分に問いかけてくる様々な位相の問題に向き合う為の勇気をもらえたことに感謝したいと思います。
「とき」という作品から13年ぶりに山海塾とのコラボレーションを再開したんだけど、とっても心配してたからすごく嬉しくて、今日はまだ見てない友人達に電話してお勧めしてました。